スイカの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数、発芽難易度−難しい?簡単?−育て方
スイカの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数、発芽難易度−難しい?簡単?−育て方
種の外観
種の大きさ、重さ
スイカの種はいわゆるスイカ割りをしたときに飛び散る黒い種子そのものです。
たねは乾燥している状態なのですが、乾燥すると普段食べているスイカの中にある黒い種のように光沢があってつやつやとしていません。
黒色が薄くなり艶はなく、少しでこぼことした感じがしています。これが乾燥しているか、水分を豊富に含んでいるかの違いです。
小さくても、小さすぎるということありませんが、決して大きくはなく、乾燥しているため、重さはほとんど感じられません。
種の構造
スイカの種は黒い硬い殻に覆われていて、しっかりと中の種を守っています。
このため、かなり硬い種が乾燥しているとさらに硬くなっています。
スイカを食べているときに、必ず誰しも間違って黒い種を食べてしまうことがあるでしょう。
白い種であればやらかくてあまり気にせず噛み砕くてしまのですか黒いのだと少し硬い感触がして嫌な味がします。
この白から黒に変わる時、種が熟成されるときに非常に硬さができるのだと思います。
この殻はかなり厚めです。
種まきの発芽の難しさ
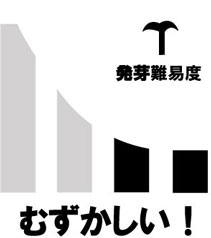
発芽適温:25〜30度、発芽日数:4〜1週間
スイカの種まき方法
スイカの種まきほど難しいものありません。
しかし、それほど難しいということは言われていません。
それは、発芽適温が25度から30度という温度で発芽できるからです。
まず、この温度で発芽できることはそこまで難しいとはいうことはないようです。
また、必ず水に浸すというものだと言われています。
種から根が伸びてくるまでとか、2、3日とか、一晩など、一体どれくらい見せつけるのはいいですかという質問などあったりしますが、専門的なところの意見だと、一晩でよく、それ以上、水分を吸いすぎて発芽が遅くなってしまうということでした。
スイカの種を水につけすぎると発芽率が悪くなるようです。
また、ある種苗会社のスイカの種は水につけていけないと書いてありました。代わりに、撒いた後に新聞紙を上からかぶせるとありました。
この違いがどれほどの意味があるのかよく起こりませんが、とにかく、スイカの種は改良されて珍しいものになってくるととても高くなってきます。
昔作っていたような懐かしいスイカを作ってもあまり人気が出なくて、そんなに高値では売れないからです。
珍しい品種が人気出るわけです。1個1000円で売れるスイカより、1万円で売れる方が収入を得るためのことを考えればいいです。
種なしスイカや、オレンジ色のスイカ、また果皮が黒いものなど、歯触りがシャリシャリしているようなもの、様々なスイカが品種改良でつくられています。
たしかに、黄色いスイカよりもオレンジ色のスイカはなんだか甘そうに見える気がします。
これらのスイカのはとても魅力的で作りたいと思うのですが、種がものすごく高いのでどうしてもスイカの発芽うまくいかないと躊躇してしまいます。
一応、一般的にいわれているように種を水につけてセルトレイにまいてみました。
この時は自然の太陽の光だけで窓辺で発芽させようと試みました。
しかし、結果から言って失敗でした。それは最初の一日、2日は天気が良かったので日光があたり、セルトレイ自体が30度を越えるくらいに暖かくなっていました。
しかし、その後天気が変わりやはり温度が上がりませんでした。
その後また天気が良くなったのですが、発芽まで4日から1週間と結構速いのです。つまり、短期間に発芽させないといけないのだと思います。そのため少しでも天気が悪くなってくると、発芽できる日数過ぎてしまい種がダメになってしまい、うまく発芽できなくなると考えられます。
おそらくスイカは、自然下では種を動物つ食べさせて遠くまで運び、そして繁栄していたのと思いますが、野生のスイカが自然的に発芽するには相当な高温性気候が必要だったと思います。
そのために短い短期間だけ暑くてもだめで、高温状態をキープしているような場所、砂漠のような場所の近くの地域などが考えられます。
とてもじゃないですがこれに近い気候は、日本の天気では真夏以外は難しいようです。
確かに夏の猛暑日が続いて記録更新と言われているような最も暑い時期に、スイカが勝手に発芽してくることがあります。これはそれまでに収穫し損ねて割れてしまったスイカのこぼれ種が落ちたものですが、それが発芽するのがちょうど8月の最も熱い期間でした。
このことからもスイカが発芽するような暑さというのは、信じられないくらいの暑さなのだと思います。
おすすめのページ

-
ディルとはハーブの一種で、魚料理やピクルスなどに用いられることが多いものです。独特のふさふさとした毛のような葉が印象的です。 しかしながら、それ以上に、この種の見かけも超一流に変わっています。構造はよく分かりませんが、何か2つが1組になっているように見えます。

-
これは超拡大写真です。虫眼鏡で大きくして見ているのと同じようなくらい拡大しています。 実際には、肉眼では見えません。このような模様やスジがあることなんて分かりませんでした。超クローズアップ撮影で撮った写真を拡大してみて初めて見えてきたものです。

-
さらにトマトの種の表面を拡大してみると、棘がたくさんあり、表面がみえないくらいに埋まっています。 これは野草がセーターに付いてどこかへ運ばれるような感じです。 トマトの場合は、何かから守っているということが考えられます。 細菌、菌類、小さい昆虫類からこのトゲトゲで種を守っているかもしれません。





