春菊(シュンギク)、しゅんぎくの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数、発芽難易度−難しい?簡単?−育て方
春菊(シュンギク)、しゅんぎくの種まき方法−時期、発芽適温、発芽日数、発芽難易度−難しい?簡単?−育て方
種の外観
やはり、菊というだけあって、菊の花が咲き、菊の種になります。
種の大きさ、重さ
大きさは中くらいですが、花びらのような殻に入っていてとても軽くてパラパラとしています。

種の構造
外殻は野草のように、花の一部か何かがそのまま乾燥して付いているような感じで、中に何かが入っているという感じです。
種まきの発芽の難しさ
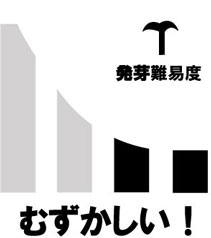
発芽適温:15〜20度、発芽日数:3〜5日
種まき時期:10〜11月頃(平野部)
春菊の種まき方法
種が薄いので、土はうっすらとかぶせればいいという種だと思います。一般的には種の厚さ*2.5倍の土をかぶせると言われています。
しかし、このあたりはアバウトで、とりあえず、かぶさっていればいいというものです。ただ、深く播くのは、発芽しない原因になりますので、気をつけた方がいいです。
シュンギクの難しさは、出来る限り早く種を播いて、年内、冬場に鍋に入れたいという気持ちとは裏腹に、暑いと発芽しにくいという特性があります。
20度以下という条件ですと、かなり、限られてきて、平野部でも10月の気温じゃないかと思われます。しかしながら、シュンギクを苗で植えるというのは聞いたことがないようにあまり、行われませんし、ホームセンターでも春菊の苗は売られていません。
でも、ここで、あえて自分で作ってしまいます。 植える時期は十分に気温が下がっていないと、枯れて消えてしまいますので注意が必要ですが、現在の春菊は枝を切って収穫するという方式のため、いくらでも収穫しつづけることができます。
そのため、苗で株が売られていてもいいくらいのですが、種しかありません。ただ、春には菊の花が咲いてしまい、食べるときに、花ごと食べれていい気分ですが、その後も、栽培し続けるとどうなるでしょうか?
たしかに、育っていきますが、冬の野菜であり、夏前には枯れてしまいます。ただ、菊だけあって、いろいろな成分が入っていて、防虫効果がありそうなので、夏の栽培というのも成功させてみたいところです。
また、種がかさばるので、ある程度播いて、しばらく待っていたら、ほんのすこししか生えて来なかったなどということがあります。
発芽率もよくなく、低めですので、多めに播いてしまうのがいいかと思います。
植え替えするつもりで、一度どこかで発芽させてから、定植するのがいいかと思います。

中葉シュンギクの双葉です。
丸くてとても小さく、弱々しい感じです。これがシュンギクになるとは想像しにくい姿です。最初の成長がゆっくりであることからも納得できます。

大葉春菊とも言われる仲間の1つの中村系シュンギクというものです。
こちらの双葉は肉厚でなんだかしっかりとしています。
野性味あふれる固定種だから、原種の強さがでているのかもしれません。
菊には色々な菊がある、切り花、除虫菊、春菊、、、野菊
数えきれないくらいの菊が日本国内にあって、まあ、品評会などではその多さが圧倒しています。野菊なんていうのが原種なのか、とにかく、国の花なんて 言われているくらいですから、とにかく、国内では一番多い、盛んな種類の花が菊だと思います。
菊はありがたいものという気持ちもあったのかもしれません。とくに昔は、そういうことがあったのかもしれません。それで食べるようになった菊が春菊。 ただ、春に花が咲くという意味の春菊というネーミングだと思いますが、とにかく、野菜として食べるのはめずらしいことです。
除虫菊のように、虫が寄ってこないようなものがあり、たしかに、春菊も害虫に食べられるということはなく、一種の匂いを出していて、これが化学物質で なにかの作用をしているようにみえます。
人には害がないのでしょう。しかし、虫はよらないから、蚊取り線香として有名で、この国の昔の伝染病の予防に一役かったともいえるかもしれません。
いまでは、蚊は多いし、夏でも冬でも、防御しない人が水たまりの多い都会の公園などではウロウロしていますから、いいえさもいいところです。そういう こともあってか、今まで確認されていない病気が蚊によって媒介されたりしています。
そういうことを防ぐためには自然の除虫菊などがいいわけです。
そして野菊というくらいに、野には菊がはえています。小さい、小径の菊はたくさんあります。昔はこういったものが、仏壇に供えられていたものだったのでしょう。 いまでは、大輪の菊がとても流通していてそちらがメインで、家庭で育てるような菊は小さいものが多いです。
そして、家庭菜園で育てる菊は、野菊のような小さいもので、花の色が黄色一色で、これも食べれるのですが、たまに花が売られています。 まるで、金粉のように食べても害はないが、食べて美味しいか?っていうと、味はない。という感じのものが有ります。
こういうものがあるので、ほんとうに菊が好きな人が多いんだなと思います。
そのため、家庭菜園では、菊などというのは、春菊くらいしか無いと思いますが、普通は食べないタイプの植物です。これを美味しいといって食べているわけです。
でも、自然の野草は食べないほうがいいです。
ある意味、家庭菜園でも、菊というのは異色の存在である野菜です。しかし、鍋に入れた春菊は日本料理には必需品でこれがないと、始まらないでしょう。 そのため、春菊栽培は非常に盛んです。
春菊には2つの形態があり、いわゆる、野菊のような直立で何本もに分かれて伸びていくものと、1本が中止となって、葉が短い茎にロゼッタ上に付いていく いわゆる、レタスキャベツ型というのでしょうか?そういう感じで密集したものがあります。
当然、栽培効率から言えば、何本も別れたほうが、切り取ってどんどんと食べられますからそちらがいいわけですが、少し古い、昔の春菊は株どりといって、 そういう、ひとかたまりのキャベツのような塊の春菊を株ごと収穫して食べていました。
こちらのほうが、圧倒的に柔らかく、優しい味がします。断然、美味しいです。
いまのものは、匂いがキツく、菊の香りって感じが強いです。あとは、緑が濃く、葉もしっかりとしていて、硬めです。どうせ、火を通してひたひたにするんだから、 いいといえばいいのでしょう。昔の春菊は生でも柔らかくて食べられるくらいに良いものでした。これも、種は売っていますので、今でも育てれば、 自分で食べることが出来ます。
中村系春菊などと呼ばれているようです。他にもたくさんの呼び名があるでしょう。これも、収穫したら一応、根本が残っていれば、また、時間はかかりますが、 生えてきて収穫することができます。家庭菜園向きです。
ただし、発芽率は、今も昔も良くないので、たくさん多めに播いておく方がいいと思います。
おすすめのページ

-
ディルとはハーブの一種で、魚料理やピクルスなどに用いられることが多いものです。独特のふさふさとした毛のような葉が印象的です。 しかしながら、それ以上に、この種の見かけも超一流に変わっています。構造はよく分かりませんが、何か2つが1組になっているように見えます。

-
これは超拡大写真です。虫眼鏡で大きくして見ているのと同じようなくらい拡大しています。 実際には、肉眼では見えません。このような模様やスジがあることなんて分かりませんでした。超クローズアップ撮影で撮った写真を拡大してみて初めて見えてきたものです。

-
さらにトマトの種の表面を拡大してみると、棘がたくさんあり、表面がみえないくらいに埋まっています。 これは野草がセーターに付いてどこかへ運ばれるような感じです。 トマトの場合は、何かから守っているということが考えられます。 細菌、菌類、小さい昆虫類からこのトゲトゲで種を守っているかもしれません。








